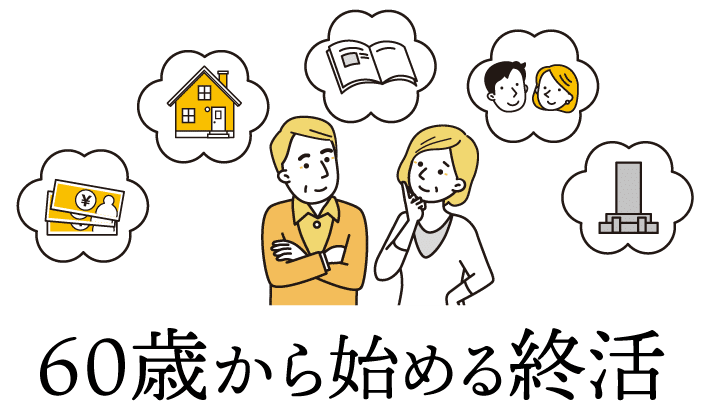これまで、当ブログでは年金について、エンディングノートについて、断捨離について、子なし夫婦の葬儀について、子なし夫婦のお墓について、などを取り上げてきましたが、今回のテーマは『年金』です。
60歳になると、いよいよ「年金をどう受け取るか」を具体的に考えるタイミングになります。
年金は、私たちの老後の生活を支える大事な収入源。
でも、終活を始めたばかりの私たち。
「いつから受け取るのが得なのか?」
「そもそも年金だけで生活できるの?」
「貯蓄はどれくらい必要?」
など、悩むポイントが多いものです。
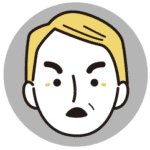
そろそろ年金のこと、ちゃんと考えたほうがいいんじゃない?
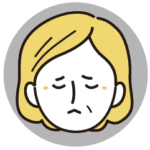
うん。でも、年金っていつからもらうのがベストなのかよく分からないんだよね
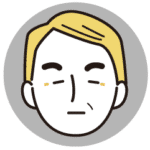
60歳からもらえるらしいけど、65歳まで待ったほうが得とか言うし…
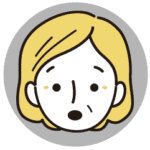
結局、どっちがいいのかって人それぞれなんだろうけど、ちゃんと仕組みを知っておかないと損しそう…!
今回は、年金の受給開始時期を決める際に押さえておきたいポイントや、年代別の年金受給額の目安、専業主婦の年金、老後破産を防ぐために必要な貯蓄額などを分かりやすくまとめてみました。
年金の仕組みをしっかり理解して、損しない選択を一緒に考えていきましょう!
- 60歳から受給できる年金の種類と金額
- 受給開始時期によるメリット・デメリット
- 老後に必要な貯蓄額の目安
- 年金をもらいながら働く
60歳になったらもらえる年金とは?
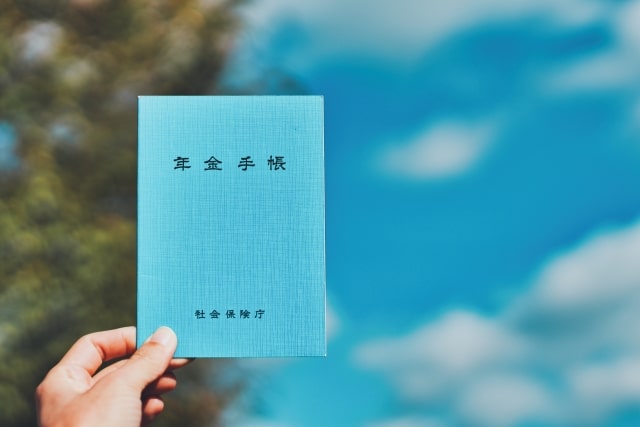
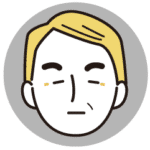
「60歳になったらすぐに年金がもらえるのかな?
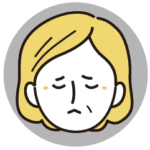
うーん…65歳からって聞いたことあるけど、60歳からもらう方法もあるのかな?
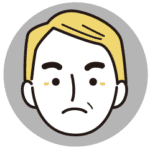
国民年金とか厚生年金とか種類があるし、条件とかも難しそう…
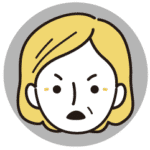
よし、整理してみよう!
60歳になると、年金の受給をどうするか考える時期。
でも、一口に「年金」と言っても種類があり、それぞれ仕組みが違います。
ここでは、60歳からもらえる年金の種類と条件について解説します。
年金には「国民年金」と「厚生年金」がある
日本の公的年金制度には、大きく分けて 「国民年金」 と 「厚生年金」 があります。
国民年金はシンプルな仕組みで、40年間きちんと納めていれば満額もらえます。
ただし、支給額はそこまで多くないため、老後の生活には 貯蓄や個人年金などの準備が必要 になります。
厚生年金は、給与額や加入期間によってもらえる金額が変わります。
会社員や公務員として長く働いていた人は、国民年金と比べて受給額が大きくなります。
60歳からもらえる年金
60歳から年金をもらう方法は、大きく分けて 「特別支給の厚生年金」 と 「国民年金の繰り上げ受給」 の2つがあります。
ただし、どちらも 条件やデメリットがある ため、慎重に考える必要があります。
かつては60歳から支給されていた厚生年金ですが、年金制度の改正により、今の60歳の人は 原則65歳から受給 となっています。
ただし、特定の条件を満たす人は、60歳から一部の年金を受け取ることができます。
例えば、本来65歳から月6.5万円もらえるはずの人が 60歳から受給すると、約4.9万円に減額 され、その金額は生涯変わりません。
早くもらえるのはメリットですが、 長生きするほど損 になる可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
65歳からもらう通常の年金と何が違うのか?
60歳から受給できる年金には、減額や条件があるのに対し、65歳からの通常の年金は満額受け取れるのが大きな違いです。
| 受給開始年齢 | もらえる年金 | 減額の有無 |
|---|---|---|
| 60歳(繰り上げ受給) | 受給額が最大24%減額 | 一生涯減額される |
| 60歳(特別支給の厚生年金) | 一部のみ受給可能 | 一定の条件あり |
| 65歳(通常受給) | 満額支給 | 減額なし |
長生きすればするほど、60歳で受け取るより 65歳まで待ったほうがトータルの受給額は多くなる 傾向にあります。
とはいえ、 「貯蓄が少ない」「早めにお金が必要」 という人にとっては、60歳から受け取る選択肢もアリです。

年金の平均受給額:実際にいくらもらえるの?
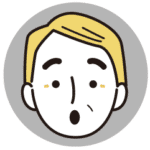
年金って、結局いくらもらえるのかな?
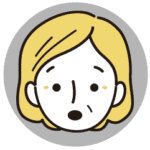
平均額とかシミュレーションを見てみたら、なんとなくイメージがつかめるかもね
年金制度は仕組みが複雑ですが、実際の受給額がわかると老後の生活設計がしやすくなります。
ここでは、現在の年金受給者が実際にどれくらいもらっているのか、また 夫婦での受給シミュレーション も交えて解説します。
現在の年金受給者の平均額(国民年金・厚生年金)
厚生労働省のデータによると、現在の年金受給者が受け取っている金額は 国民年金のみの場合と、厚生年金とセットで受け取る場合で大きく異なります。
国民年金のみ:平均月5.5~6.5万円
- 40年間保険料を納めた場合の満額:月約6.5万円(令和6年度)
- 実際の平均受給額:月5.5万円前後(未納や免除期間がある人が多いため)
国民年金だけでは 生活費をまかなうのは厳しい のが現実。家賃や医療費を考えると、貯蓄や他の収入源が必要になります。
厚生年金+国民年金:平均月15万円前後
- 会社員・公務員の平均受給額:月14~15万円(国民年金+厚生年金)
- 夫婦合算(夫が厚生年金・妻が専業主婦の場合):月22万円前後
厚生年金は 加入期間と収入によって受給額が大きく変わるため、これより多い人もいれば少ない人もいます。とはいえ、国民年金だけに比べると、かなり余裕のある金額です。
夫婦での受給額シミュレーション(専業主婦・共働き世帯など)
夫婦の働き方によって、老後にもらえる年金額には大きな差が出ます。いくつかのパターンでシミュレーションしてみましょう。
① 夫が会社員・妻が専業主婦(年金第3号被保険者)
- 夫の年金(厚生年金+国民年金):約15万円
- 妻の年金(国民年金のみ):約6.5万円
- 合計:21.5万円
このパターンは、昔の日本で一般的だった「夫が働き、妻が専業主婦」のケース。
ただし、生活費としてはそこまで余裕があるわけではないため、持ち家の有無や貯蓄が重要になります。
② 夫婦共働き(2人とも厚生年金あり)
- 夫の年金(厚生年金+国民年金):約15万円
- 妻の年金(厚生年金+国民年金):約10~12万円
- 合計:25~27万円
共働きで長く厚生年金に加入していた場合、夫婦合算で月25万円以上になることも。
老後の生活に余裕ができるので、趣味や旅行も楽しみやすくなります。
③ 夫婦ともに自営業(国民年金のみ)
- 夫の年金(国民年金のみ):約6.5万円
- 妻の年金(国民年金のみ):約6.5万円
- 合計:13万円
自営業やフリーランスの夫婦は、厚生年金に加入していないため、年金だけでは生活が厳しくなるケースが多いです。
この場合、貯蓄や私的年金(iDeCoや国民年金基金など)を活用するのが必須になります。
他には 老後資金に特化したFP無料相談 を利用してみるのも手です。
- 厚生年金があると老後の年金額は多めだが、それでも生活費+余裕資金を考えると貯蓄は欠かせない
- 国民年金のみの場合は、年金だけでは暮らせない可能性大!
別の収入源を確保する必要あり - 共働き世帯のほうが年金の受給額は多く、老後の選択肢が広がる
リクルートが運営する
老後資金に特化したFP無料相談がおすすめ!
老後資金の悩みをお金の専門家(FP)への無料相談ができるサービスです。
自宅でオンライン相談もできますよ。
家計の状況を丁寧にヒアリングし、最適なライフプランを提案してもらいましょう。
年金以外に、どのくらいの貯蓄が必要か?

『老後2000万円問題』っていうけど、実際そんなに必要なの?
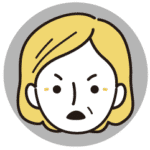
じゃあ、どのくらい貯めれば安心なのか、一緒に考えてみよう!
「老後破産」という言葉を耳にすると、「そんなに貯蓄がないとダメなの⁉」と不安になりますよね。
でも、本当に2000万円も必要なのか、実際の生活費はどのくらいかかるのかを具体的に見ていくと、無理のない資金計画が立てられます。
「老後2000万円問題」は本当に必要?
2019年に金融庁が発表した「老後2000万円問題」は大きな話題になりました。
これは、夫婦の年金収入だけでは生活費が足りず、30年間で約2000万円の不足が生じる という試算でした。
夫婦での年金収入+貯蓄でどこまで生活できるか
例えば、以下のような家庭では、必要な貯蓄額が大きく変わります。
このように、持ち家か賃貸か、支出をどこまで抑えられるかで必要な貯蓄額は変わります。
最低限必要な老後資金(シミュレーション)
それでは、具体的に「月20万円」「月30万円」の生活費で考えてみましょう。
旅行や趣味を控えれば、比較的シンプルな生活は可能
趣味や旅行も楽しみたいなら、それなりの貯蓄が必要
貯蓄が少ない場合の対策
「老後資金が足りない!」となった場合でも、できることはたくさんあります。
生活費の見直し(固定費削減、住まいの選び方)
まず生活費の見直しをしてみましょう。
最近はシニア向けのシェアハウスやコンパクトな持ち家も注目されています。
住まいの工夫で、生活費を抑えるのも一つの手です。
働きながら年金をもらう方法
「年金だけで生活するのが不安…」という場合は、年金をもらいながら働く のもアリ!
年金をもらいながら働くことについてはこちらで詳しく解説します。
年金と合わせて 月5~10万円でも収入があると、貯蓄の減りを抑えられるので、安心して生活できます。

専業主婦の年金はどうなる?
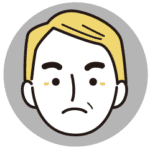
そういえば、専業主婦の年金ってどうなるの?
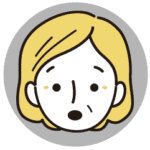
うん、私も気になってた!働いてないと年金が少ないって聞くけど…
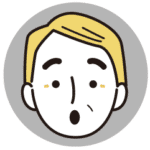
うちは今のところ俺が厚生年金で、君は専業主婦だから、第3号被保険者になるんだよね?
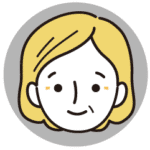
そうそう!じゃあ、専業主婦の年金について整理してみよう!
第3号被保険者の年金受給額
専業主婦(または扶養に入っているパート主婦)は、厚生年金には加入していない ため、基本的に もらえるのは国民年金のみ です。
例えば、結婚前に会社員だった期間がある場合は、その分の厚生年金が加算されますが、専業主婦のまま年金を受け取ると、基本は国民年金だけ です。
夫の厚生年金と合算したときの目安
専業主婦世帯の場合、夫が厚生年金を受け取ることで、世帯全体の年金額が増えます。
[夫婦の年金の合計額(目安)]
| 夫の年収(現役時代) | 夫の厚生年金 | 妻の国民年金 | 合計(月額) |
|---|---|---|---|
| 約400万円 | 10万円 | 6.5万円 | 16.5万円 |
| 約500万円 | 13万円 | 6.5万円 | 19.5万円 |
| 約600万円 | 15万円 | 6.5万円 | 21.5万円 |
※ 実際の年金額は加入期間や支払額によって異なります。
このように、夫の厚生年金+妻の国民年金で、夫婦合わせて15~22万円ほど になるのが一般的です。
共働きとの受給額の違い
もし、専業主婦ではなく共働きだった場合、どう違うのでしょうか?
共働きだと、妻も厚生年金に加入するため、年金額が増えます。
[夫婦の年金の合計額(目安・共働き)]
| 夫の年収 | 夫の厚生年金 | 妻の年収 | 妻の厚生年金 | 合計(月額) |
|---|---|---|---|---|
| 500万円 | 13万円 | 200万円 | 7万円 | 20万円 |
| 600万円 | 15万円 | 300万円 | 9万円 | 24万円 |
| 700万円 | 17万円 | 400万円 | 11万円 | 28万円 |
専業主婦と共働きを比較すると、共働きの方が世帯全体の年金額が多くなる のがわかりますね。
- 専業主婦の年金は基本「国民年金のみ」なので、月約6.5万円が目安
- 夫の厚生年金と合わせると、世帯全体で月15~22万円くらい
- 共働きだと、妻の厚生年金分が加わるため、年金額が増える
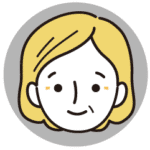
なるほど…やっぱり共働きの方が年金的には有利なんだね
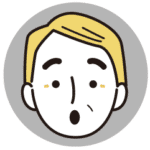
でも、その分働く負担もあるし、どっちがいいかは家庭の考え方次第かな
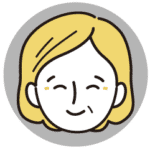
「うん!専業主婦でも年金はもらえるし、足りない分をどう補うか考えればいいね!
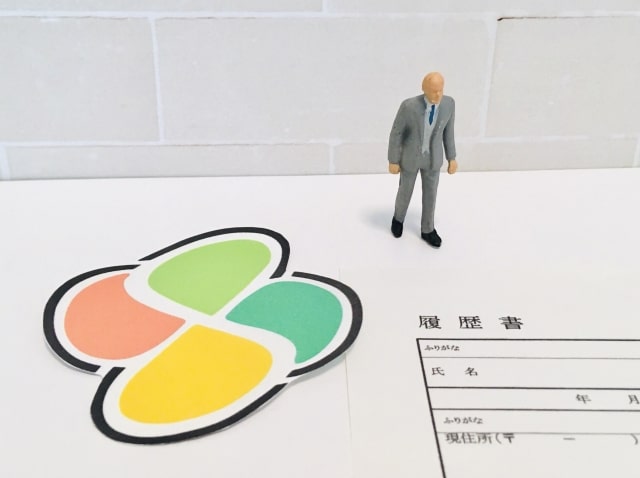
年金をもらいながら働くことは可能?
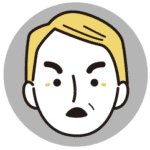
年金をもらいながら働くってアリなのかな?
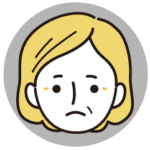
うん、最近はシニア世代でも働く人が増えてるみたい。
でも、働くと年金が減るって聞いたことあるよ

そうなんだ…せっかく年金もらえるのに減っちゃうのはちょっとなぁ
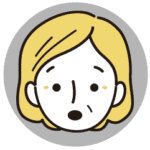
そう思うよね。
でも、2022年に制度が改正されて、前よりは働きやすくなったみたい!
在職老齢年金制度とは?
「在職老齢年金」という制度は、年金を受け取りながら働く人の年金額を調整するルール です。
一定額以上の収入があると、年金が減額される
60歳以上の人が厚生年金に加入しながら働く場合、収入が一定額を超えると年金の一部がカット されます。
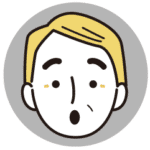
つまり「65歳以上で月47万円以下の収入なら、年金は減額されない」ということ!
[例:60歳の人が働きながら年金をもらうケース]
| 月収(給与+年金) | 年金の減額 |
|---|---|
| 25万円 | 減額なし |
| 30万円 | 一部減額 |
| 40万円 | さらに減額 |
以前はもう少し厳しいルールでしたが、2022年の改正で減額される基準が緩和 され、働きながら年金をもらいやすくなりました!
シニアの働き方の選択肢
シニア世代でも、自分のライフスタイルに合わせていろいろな働き方が選べます!
最近は「シニア向けの求人サイト」も充実しているので、自分に合った仕事を探しやすくなっています!
短時間勤務や在宅ワークを活用すれば、年金をもらいながら無理なく働けるのがメリットですね!

働きながら年金をもらうのも意外とアリかも!
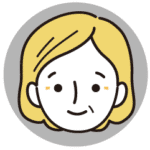
うん!無理せず、ちょっとした収入を増やすのもいいよね

結局、年金はいつからもらうのが正解?
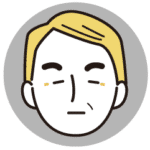
年金って、早くもらうほどいいのかな?
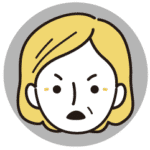
うーん、それが一概に言えないのよね。60歳からもらうと減るし、70歳まで待つと増えるし…

なるほど。でも、長生きするかどうかなんて分からないよなぁ
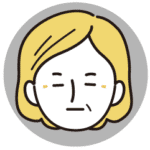
そこが難しいところ!だからこそ、自分に合った選択を考えないとね
選択は人によりますが、重要なのは「年金+貯蓄+働き方」のバランスを考えて決めるのがベストです。
自分のライフスタイルや健康状態を考えて、後悔のない選択をしましょう!
- 60歳からの受給が向いている人
生活資金に余裕がなく、すぐに年金が必要な人 - 65歳からの受給が向いている人
標準的な生活を考え、無理せず受け取りたい人 - 70歳からの受給が向いている人
長生きする可能性が高く、年金を増やしたい人
60歳から受給 → 生活費が厳しい人向け
「繰り上げ受給」を選べば、60歳から年金を受け取ることが可能 です。ただし…
デメリット
- 1か月早めるごとに0.4%減額(60歳で開始すると最大24%減)
- 一度繰り上げると元に戻せない
- 65歳になるまで「加給年金」が受け取れない(※厚生年金の加算)
こんな人に向いている!
- 貯蓄が少なく、60歳からの収入が不足しそうな人
- 60歳以降も働く予定がなく、年金が頼みの綱な人
- 長生きする自信がない人(※ただし、長生きすると損するリスクあり)
[例:65歳までの年金総額の比較(仮)]
| 開始年齢 | 1年の年金額 | 65歳までの総額 |
|---|---|---|
| 60歳 | 78万円 | 390万円 |
| 65歳 | 100万円 | 0万円 |

「60歳からもらうと65歳時点で390万円受け取れるけど、月の年金額は少ない」ということですね。
65歳から受給 → 一般的な標準プラン
現在の制度では、65歳から受給するのが標準的なスタイル です。
メリット
- 減額なしで満額の年金を受け取れる
- 厚生年金加入者なら加給年金ももらえる
(※一定の条件あり)
デメリット
- 60~65歳の間は年金収入がゼロ
(→貯蓄や働き方が重要)
こんな人に向いている!
- 60~65歳の間は貯蓄や働きながら生活できる人
- 「平均的な年金受給額で問題ない」と考える人
70歳まで繰り下げ → 長生きするほどお得
「繰り下げ受給」を選ぶと、1か月遅らせるごとに0.7%年金が増額 されます!
メリット
- 70歳まで繰り下げると、最大42%増額
- 終身で増額された年金を受け取れるため、長生きすればするほどお得
デメリット
- 70歳までの無収入期間をカバーする貯蓄や収入源が必要
- もし早く亡くなると損になる
こんな人に向いている!
- 健康に自信があり、長生きする可能性が高い人
- 貯蓄や働く手段があり、70歳まで年金なしでも生活できる人
[70歳受給の年金額(仮)]
| 開始年齢 | 1年の年金額 | 10年受給した場合 |
|---|---|---|
| 65歳 | 100万円 | 1000万円 |
| 70歳 | 142万円 | 1420万円 |
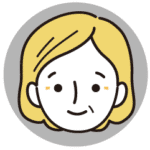
70歳まで我慢すれば、65歳から受給するよりも年間42万円増える計算になります!

年金受給の手続き:いつ、どうやって申し込む?
年金を受け取るための手続きの流れ を整理していきましょう!
いつから手続きが必要?
年金は 自動的には支給されません! 受け取り開始の 3か月前 から手続きが可能になります。
| 受給開始年齢 | 手続き開始時期(誕生月基準) |
|---|---|
| 60歳 | 57歳9か月~ |
| 65歳 | 62歳9か月~ |
| 70歳 | 67歳9か月~ |
例えば、65歳から受給する場合 は、62歳9か月ごろに案内が届く ので、忘れずにチェックしましょう!
年金受給の申し込み方法
年金を受け取るためには、手続きが必要です。
受給開始年齢の3か月前になると、日本年金機構から 「年金請求書」 が届きます。
必要書類を準備し、手続きは 年金事務所の窓口か郵送 で行えます。
窓口での申請
全国の 年金事務所 に行けば、職員が手続きのサポートをしてくれます。
(予約推奨! 事前に予約すればスムーズに進みます。)
郵送での申請
自宅から郵送でも申請OK!必要書類をそろえて、日本年金機構に送付します。
(記入ミスに注意! 不備があると受理されず、手続きが遅れる可能性あり。)
いつから年金が振り込まれる?
無事に手続きが完了すると、申請した月の翌月から振り込みが開始されます。
年金の振り込みスケジュール
年金は 偶数月の15日 に、2か月分まとめて振り込まれます!
| 振込月 | 対象期間 |
|---|---|
| 2月 | 12月~1月分 |
| 4月 | 2月~3月分 |
| 6月 | 4月~5月分 |
| 8月 | 6月~7月分 |
| 10月 | 8月~9月分 |
| 12月 | 10月~11月分 |
例えば、4月に年金の受給を開始すると、最初の振り込みは 6月15日(2か月分)になります。
初回の振り込みは 2~3か月ほど遅れることもあるので、受給開始直後は生活費を確保しておくことが重要です!
申請し忘れた場合、5年以内なら遡ってもらえます。
年金は「請求しないともらえない」制度ですが、請求の時点から過去5年分まで 遡って受け取ることができます。
例えば…
- 65歳で受給開始予定だったのに、70歳まで手続きを忘れていた
→ 申請すれば 65歳からの5年分(60か月分)は一括で受け取れる - 70歳を超えてしまった場合
→ 70歳の5年前(65歳)までの分しか受け取れない
(それ以前の分は消滅!)
もらい忘れは損なので、早めの申請を忘れずに!
年金について:最後に…
「年金はいつからもらうのが正解?」という問いに、絶対の正解はありません!
大切なのは、自分たちのライフスタイルや貯蓄、働き方を考えながら最適な選択をすること です。
みなさんも、ご自身の状況に合わせて、年金の受給タイミングをじっくり検討してみてくださいね!
よろしければポチっとしていただければ励みになります!