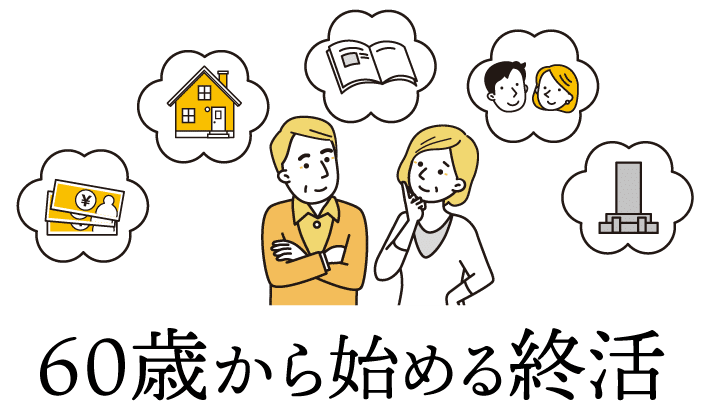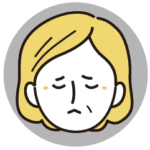
お隣んち、この先お墓参りする人がいなくなるから、墓じまいするんだって。
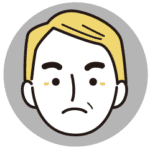
寂しいけど他人事じゃないぞ。
われわれの墓についても考えておかないとな!
終活を進める中で、きちんと考えておかなければならないことに「自分たちの墓をどうするか」という問題があります。
特に、子孫がいない夫婦の場合、お墓を誰が管理するのか、そもそも必要なのかを考えると、悩みが尽きませんよね。
かつては「家族が代々お墓を継ぐ」のが当たり前でしたが、今は価値観が変わりつつあります。
墓じまいをする人も増えていますし、永代供養や樹木葬、散骨など、新しい供養の選択肢も増えています。
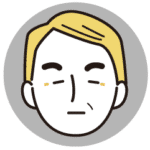
そもそも供養のしかたもいろいろあるし、
具体的な費用面のことも調べておかないとね。
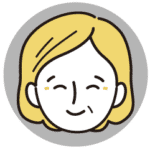
そうね、私達に合うのは何か、後々困らないように決めておきましょう。
前回は葬儀について考えてきましたが、今回は、子なし夫婦のお墓問題について、さまざまな選択肢をわかりやすく紹介しながら、一緒に考えていきたいと思います。
私たち夫婦も悩みながら調べたので、同じように考えている方の参考になれば嬉しいです!
では、さっそく見ていきましょう!
- 墓を持つことの意味や維持の問題
- 墓を持ってる場合と持ってない場合の選択肢
- 墓じまいについて
- 様々な供養の形
子なし夫婦のお墓問題

お墓は「家族が代々受け継いでいくもの」というイメージが強いですよね。
でも、子どもがいない夫婦にとっては、その前提が当てはまりません。
私たちが亡くなった後、誰が面倒を見てくれるのか?
そもそも、お墓は本当に必要なのか?
こうした疑問は、終活を進める上で避けて通れません。
最近では、「お墓を継ぐ人がいないから」という理由で墓じまいをするケースも増えています。
一方で、「やっぱり自分たちの遺骨を納める場所が欲しい」と考える人もいて、選択肢はさまざまです。
では、子なし夫婦にとってお墓を持つことの意味や、その維持の問題について、もう少し深掘りして考えてみましょう。
お墓を持てば維持費もかかる
お墓を持つことには、さまざまな意味があります。
一方で、お墓を持つことには 維持の問題 もついて回ります。
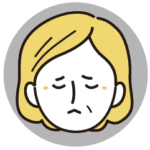
「自分たちだけでお墓を持つことに不安を感じる」という人も増えてるみたいね。

まあ、いろんな考え方があるからね。
寂しいけど現実を考えると仕方ないのかもしれない。
では、そもそも従来の「家墓」制度とはどういうものだったのか?
そして、それが今どう変わってきているのかを見てみましょう。
家墓は時代とともに変化している
昔は「家のお墓=家族の責任」という考え方が一般的でした。
親が亡くなれば子どもが継ぎ、そのまた子どもが継いでいく…。
こうしてお墓が代々守られてきたわけです。
けれど、現代では次のような変化が起こってきています。
家墓(いえはか・いえぼ)とは
家族や親族の遺骨を共同で納めるお墓で、先祖代々受け継がれています。
累代墓(るいだいぼ)とも呼ばれます。
墓石には「○○家の墓」などの家名が刻まれてい一般的な墓ですが、明治末期に火葬が増えたことに伴い急速に増加し、昭和初期以降に主流となりました。
一昔前までは長男が引き継ぐのが一般的だったが、現代では宗教不問の霊園も増えたため、親族・子孫で使用することが多くなりました。
対して個人のお墓は個人墓になります。

墓の継承者がいなくなる問題
すでにお墓を持っている場合、子どもがいない夫婦にとって 「このお墓をどうするか?」 が大きな課題になります。
「墓じまいをするのがいいのか、それとも維持するのか?」
「自分たちが亡くなった後、誰が面倒を見てくれるのか?」
こうした悩みを抱えている方は多いと思います。
ここでは、すでにお墓を持っている場合に考えるべき選択肢について整理していきます。
墓の継承者がいなくなることで考えられる問題
お墓は、 「継承者がいることを前提」 に作られているものがほとんどです。
そのため、子どもがいない場合は、以下のような問題が生じます。
こうした問題はどうしても生じてしまいます・・・。
放置してしまうと、お墓が荒れたり、最終的に行政によって撤去されることもあるので、生前に自分達がキチンとしておかなければなりません。
そうならないために、墓じまいをするのか、それとも維持するのか、しっかり検討する必要があります。
墓じまいをする場合
「墓じまい」とは、お墓を撤去し、遺骨を別の形で供養すること。
最近では、子どもがいない夫婦を中心に、墓じまいを選ぶ人が増えています。
[墓じまいのメリット]
- 後の世代に負担をかけない
- 管理費や維持費が不要になる
- 別の供養方法(永代供養・樹木葬・散骨など)が選べる
ただし、墓じまいには費用や手続きが必要になります。墓石の撤去費用は 20万~50万円 が相場で、遺骨の移動にも別途費用がかかります。
(墓じまいについては後ほど詳しく解説いたします。)
維持する場合
「やっぱり今あるお墓を維持したい」という場合は、以下の方法を考えた方が良いと思います。
維持をするなら、「自分が元気なうちにどこまで準備できるか」がカギになるでしょう。
相談できる人がいない場合 永代供養 を選べば、寺院や霊園が供養を続けてくれるため、継承者がいなくても安心です。
お墓を持たない供養方法は?
最近では、お墓を持たずに供養する方法を選ぶ人も増えてきました。
→子なし夫婦の葬儀、お葬式は必要?現代の葬儀事情と選択肢
子どもがいない夫婦の場合、お墓を建てても守る人がいない という問題がありますよね。
「墓じまいの手間を残すくらいなら、いっそ最初から持たない方がいいのでは?」と考えるのも自然な流れです。
「お墓を残したいけど、継ぐ人がいない…」そんな場合に考えられる供養方法を紹介します。
お墓を持たない供養方法:永代供養墓
永代供養墓 とは、霊園や寺院が管理・供養してくれるお墓のこと。
[費用相場]
30万~100万円(管理費不要の場合が多い)
[メリット]
子どもがいなくても安心して供養を任せられる

お墓を持たない供養方法:樹木葬
樹木葬とは、樹木の下に遺骨を埋葬する「自然志向」の供養方法。
[費用相場]
10万~50万円
[メリット]
お墓の管理が不要、自然に還る
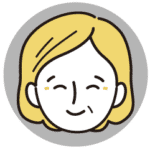
うちは跡継ぎがいないからというのもあるけど、
以前から私はできれば自然に還りたいと思ってたのよね。

そうだね、ふたりとも自然が好きだから俺らに合ってると思うよ。
私たちの世代では、「お墓は絶対に必要!」と考える人が減り、「できるだけシンプルに、負担の少ない形にしたい」という声が多くなってきました。
こうした流れの中で、永代供養墓や樹木葬など、新しいお墓の形が登場しています。
樹木葬・散骨を選んだ芸能人・有名人一覧
- 荒井注(2000年逝去)
- 立花隆(2021年逝去)
- 市原悦子(2019年逝去)
- 中島らも(2004年逝去)
- 石原慎太郎(2022年逝去)
- 勝新太郎(1997年逝去)
- 横山やすし(1996年逝去)
- 石原裕次郎(1987年逝去)
【アンカレッジの樹木葬】
豊かな自然と都市へのアクセスが良い横浜市緑区に花と緑に囲まれた庭園タイプの樹木葬。
- お寺が永代供養してくれる。
- 継承者不要でも大丈夫。
- 一人ずつや夫婦ごとに埋葬。
- 希望者はペットも一緒にお墓に入れる。
お墓を持たない供養方法:海洋葬
遺骨を粉末にして、海にまく方法。
[費用相場]
5万~30万円
[メリット]
自然に還るシンプルな供養

お墓を持たない供養方法:合同墓(合祀墓)
「お墓を建てるのは大変だけど、どこかに遺骨を安置しておきたい」という場合、合同墓(合祀墓)も選択肢になります。
合同墓は、複数の人の遺骨を同じ場所に埋葬するお墓 です。お寺や霊園が管理し、供養をしてくれるため、個別の墓を持つより負担が少なくなります。
[メリット]
- 継承者不要で供養してもらえる
- 費用が比較的安い(5万~30万円)
[デメリット]
- 一度合祀すると遺骨を取り出せない
お墓を持たない供養方法:納骨堂
納骨堂はお寺や霊園の屋内施設に遺骨を安置する方法。
一定期間後に永代供養墓に移されるケースが多いです。
[メリット]
- 天候に左右されずお参りできる
- 期限までは個別に管理してもらえる
- 費用は比較的安価(20万~80万円)
[デメリット]
- 施設によっては一定期間後に合祀される

お墓を持たない供養方法:手元供養
「お墓を作らず、自宅で供養する」というのが 手元供養 です。
例えば、
- 遺骨を小さな骨壺に入れて家に置く
- 遺骨をダイヤモンドやアクセサリーに加工する
- 遺灰をペンダントに入れて持ち歩く
こうした方法があり、最近は 「故人を身近に感じられる供養」 として選ばれることが増えています。
[メリット]
- お墓を作る必要がない
- いつでも故人を身近に感じられる
- 費用が抑えられる(3万~20万円)
[デメリット]
- 遺族がいなくなると管理する人がいなくなる
- 置き場所に困ることがある

手元供養を選ぶ場合は、最終的にどこに遺骨を納めるのかも考えておいた方がいいよね。
お墓を持たない供養方法:宇宙葬
遺骨の一部を宇宙に打ち上げる新しい供養方法
日本でも宇宙葬を扱う業者が増えており、宇宙葬の形式やプランも多様化しています。
[メリット]
- ロマンを感じられる
- 経済的負担を軽減(50万~100万円)
[デメリット]
- 詐欺やトラブルへの注意
- 実施までに時間がかかること
- 宇宙葬に関する社会的な課題
お墓を持たない供養方法:献体
献体 は、亡くなった後に医療や社会に貢献できる方法。
供養ではありませんが「社会の役に立てる形で送り出したい」と考えるなら、こうした選択肢も検討する価値があるということで、今回ご紹介します。
住居地の都道府県にある医科大学(大学医学部)か歯科大学(大学歯学部)、または、献体の会に問い合わせると良いでしょう。
[メリット]
- お墓を持たずに供養できる
- 医学生の教育や研究に役立ててもらう
- 費用がかからない(費用0円)
[デメリット]
- 事前に登録が必要な場合がある
- 遺族の同意が必要になることが多い
「夫婦墓」「ペア墓」という選択肢
調べてみたら、最近では 「夫婦墓」「ペア墓」といった選択肢が増えており、継承者がいなくても利用しやすいものが増えているそうです。
夫婦墓(個別の永代供養墓)
- 夫婦だけの区画を持ち、一定期間管理後に合祀される
- 一般的な費用:50万~150万円
夫婦用樹木葬
- 夫婦で同じ樹木の下に埋葬される
- 霊園によっては「二人用プラン」がある
- 一般的な費用:20万~80万円
夫婦向け納骨堂
- 屋内のロッカーや自動搬送式の納骨堂を利用
- 期限後に永代供養される
- 一般的な費用:30万~100万円
「夫婦だけのスペースを確保できるか?」を確認しながら、希望に合う形を選びましょう。
どの方法を選ぶかは、夫婦の価値観や費用、供養に対する考え方次第。
「夫婦二人で納得できる形」を話し合いながら決めていきましょう。

墓じまいについて
「お墓を継ぐ人がいないから、墓じまいをしよう」と決めたとしても、実際にはさまざまな手続きや費用が発生します。
墓じまいの基本的な流れ
- 親族と相談
お墓の移転や撤去について、親族間でトラブルが起きないように話し合っておく。 - 墓地管理者への相談
墓じまいを考えていることを墓地の管理者(お寺や霊園)に伝え、必要な手続きについて確認する。 - 改葬許可申請
現在のお墓がある自治体に「改葬許可申請書」を提出し、許可を得る。 - 遺骨の取り出し
閉眼供養(お性根抜き)を行い、遺骨を取り出す。 - 墓石の撤去・処分
専門業者に依頼し、墓石を撤去して更地にする。 - 新たな供養先へ移動
納骨堂や永代供養墓など、新しい供養先に遺骨を移す。
墓じまいの費用
墓じまいの費用 墓じまいには、いくつかの費用がかかります。
トータルで数十万円かかることが多いため、事前に見積もりを取りながら準備を進めるのがポイントです。
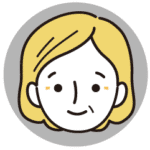
参考として一般的な目安を書きますね
- 墓石の撤去費用
10万〜50万円(墓の大きさや立地による) - 閉眼供養のお布施
1万〜5万円 - 改葬許可申請の手数料
数千円程度 - 遺骨の移動費用
新たな納骨堂や散骨費用など、選択肢によって異なる
墓じまい後の遺骨は散骨・納骨堂・永代供養墓に合祀・手元供養など様々です。

子なし夫婦のお墓問題まとめ
お墓の問題は、子どもがいない夫婦にとって避けて通れないテーマです。
今あるお墓を守るのか、それとも墓じまいをして新たな供養の形を選ぶのか。

どんな選択をするにしても、大切なのは 「自分たちらしい最期の場所を考えること」 が大切だね。
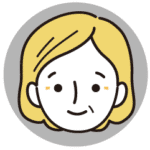
私達も後回しにしないで、この際しっかり話し合いましょう。
「まだ先のことだから」と後回しにしがちですが、終活は早めに進めたほうが、より納得のいく選択ができます。
特にお墓に関しては、手続きや費用がかかるものも多いため、 「どうしたいか」 を夫婦でじっくり話し合いましょう。
一番大切なのは、 「二人が納得できる方法を見つけること」。
もし「まだ決められない」と思うなら、まずは情報を集め、実際に見学してみるのもおすすめです。
夫婦二人だけの終活だからこそ、自由に選べる分、悩むことも多いかもしれません。
でも、最期の場所をどうするかを 二人でしっかり考え、納得のいく選択をすること が、後悔のない人生につながるはずです。
あなたとパートナーにとって 「最適なお墓の形」 を、ぜひ前向きに考えてみてくださいね。
よろしければポチっとしていただければ励みになります!